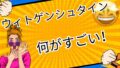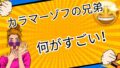「本居宣長 何がすごいのか?」――そう検索したあなたは、もしかすると学校の教科書で名前を見かけた程度かもしれません。
しかし、その名前の背後にある功績を深く知る人は、意外と少ないのではないでしょうか。
江戸時代、彼はたった一人で『古事記』全体を35年かけて読み解き、44巻にも及ぶ注釈書『古事記伝』を完成させました。
これだけでも驚異的な偉業ですが、さらに注目すべきは、医師として働きながら学問を続け、全国に約500人もの門弟を育てたという点です。
当時すでに読解が困難になっていた『古事記』を復活させ、日本人の精神文化や言語のルーツを掘り起こしたことで、彼は「国学の完成者」とまで称されています。
しかもその思想は、幕末の尊王攘夷運動や明治維新にまで影響を及ぼしました。
本居宣長のすごさは、単なる学者としての業績にとどまりません。
時代を超えて受け継がれる価値観や、日本文化への深い洞察が、多くの人々の心を動かしてきたのです。
この記事では、本居宣長が何を成し遂げ、なぜ今も語り継がれるのかを、わかりやすく丁寧に解説していきます。
本居宣長記念館(三重県松阪市)
本居宣長は1730年に松阪に生まれ
松阪で町医者を営みながら
日本の古典文学の研究を行った。
それまで誰も読めなかった古事記を
35年を費やして解読し
「古事記伝」を執筆。
師匠である賀茂真淵とともに
国学の四大人のうちの1人。
写真は撮影OKの自画自賛像🎨✨️ pic.twitter.com/URS36WLN2i— Metaro🎵 (@metaro_mech) March 21, 2025
本居宣長 何がすごい?功績と影響を徹底解説
本居宣長 何した人?簡単に!
本居宣長(もとおりのりなが)は、江戸時代に活躍した国学者であり、日本の古典を研究・解釈した人物です。
とくに有名なのは、日本最古の歴史書『古事記』を35年かけて読み解き、全44巻の注釈書『古事記伝』を完成させたことです。
彼の主な活動は、古典文学の研究、講義、そして医業でした。
若い頃は商家に育ちましたが、商売には向かず、のちに医師となって地元で開業します。
一方で、日々の診察のかたわら、日本古典に関する深い研究を続けていました。
その研究は源氏物語や万葉集などにも及び、独自の視点から注釈や解釈を加えた多くの著作を残しました。
講義を通して全国に弟子を持ち、国学という学問分野の発展にも大きく貢献しています。
つまり、古典の研究者であり教育者、そして実際に町医者としても働いた人物です。
古代日本の心や文化を解き明かそうとした姿勢は、現代の研究者たちにも受け継がれています。
本居宣長 古事記研究の意義
本居宣長の古事記研究は、日本の古代文化や言語を理解する上で、非常に重要な役割を果たしました。
特に、当時すでに読解が困難になっていた『古事記』を、独自の方法で丁寧に解釈し直したことが、高く評価されています。
『古事記』は712年に編纂された日本最古の歴史書ですが、文章はすべて漢字で書かれ、現代の言葉とは大きく異なる表記や文法が用いられていました。
そのため江戸時代には、正しく内容を読み解くことが非常に困難になっていたのです。
このような背景の中で、本居宣長は一字一句を丁寧に分析し、語源や文法の特徴、歴史的な背景までを考慮しながら、44巻にわたる『古事記伝』を完成させました。
これにより『古事記』は再び広く読まれ、古代日本の神話や価値観、文化に光が当てられるようになりました。
また、彼の研究は単なる注釈にとどまらず、日本独自の思想や精神性を明らかにしようとする姿勢が強く反映されています。
このことが、後の国学の発展や、日本人のアイデンティティに関する議論にもつながっていきました。
一方で、漢字の用法や音の読み方に関する考察は非常に専門的で、現代の読者には難解に感じられる部分もあります。
ただし、言葉の細部にまでこだわる緻密な姿勢は、学問における誠実さを象徴しているとも言えるでしょう。
このように、本居宣長の古事記研究は、古代日本の再評価につながる礎を築いただけでなく、日本語学や文献学の分野でも大きな意義を持つものとなっています。
本居宣長 代表作とその評価
本居宣長の代表作には、『古事記伝』『源氏物語玉の小櫛』『紫文要領』『玉勝間』などがあります。
いずれの著作も、日本の古典や言語、思想に深く切り込んだ内容であり、現在でも高い評価を受けています。
まず、『古事記伝』は彼の名を最も広めた書物です。
古事記の全文に対して詳細な注釈を加え、意味を一つひとつ丁寧に解釈しました。
全44巻におよぶこの大著は、35年の歳月をかけて完成されたものであり、古代の日本語や神話世界を解明するうえで欠かせない資料とされています。
次に、『源氏物語玉の小櫛』と『紫文要領』は、源氏物語の本質を「もののあはれ」という情感に見出した点で画期的でした。
従来の儒教的な道徳観で語られていた源氏物語を、感性に基づく読み解きに転換させたことで、文学の新たな価値観を提示したとも言えるでしょう。
『玉勝間』は随筆集であり、学問・人生・日本文化への考察がまとめられています。
さまざまな話題に触れつつも、言葉の使い方や思想のあり方に対する深い洞察がにじんでおり、当時の知識人層からも支持を集めました。
一方で、難解な言い回しや専門的な記述が多いため、現代人にとっては読みやすい書物とは言えません。
しかし、それでも研究者や歴史愛好家から高い信頼を得ており、学問的な価値は今も色あせていません。
このように、本居宣長の代表作は、日本文化の深層に迫る内容と、緻密な研究姿勢が融合した成果であり、江戸時代から今日に至るまで、古典研究の基盤として読み継がれています。
本居宣長 学問の姿勢と理念
本居宣長の学問に対する姿勢は、一言でいえば「誠実さと粘り強さ」に貫かれていました。
学問とは、才能よりも継続と努力が重要であるという信念を持ち、生涯を通して地道な研究を積み重ねました。
彼は、「学問というものは、長い年月を飽きず怠けずに続けることが大切である」と繰り返し語っています。
これは、どんな分野であっても、一歩一歩積み上げることが成果につながるという考え方を示しています。
実際、彼の代表作である『古事記伝』は、35年の歳月をかけて完成されたものであり、この理念が実践されていたことがよくわかります。
また、本居宣長の学問は、外来思想に依存せず、日本独自の文化や心を見つめる姿勢を重視していました。
当時の支配的な学問だった儒教や仏教を「からごころ(外来の考え)」とし、それらに頼らず「やまとごころ(日本人本来の心)」を尊重すべきだと説いています。
このような考え方は、単なる知識の習得にとどまらず、「何のために学ぶのか」「どこに立脚して物事を考えるのか」といった、学問の根本的なあり方にまで踏み込んでいます。
一方で、彼の姿勢には厳しさもありました。知識を身につけただけで満足してしまうことや、形式的に学ぶことには否定的でした。
だからこそ、宣長は「学び方はいかようでもよいが、続けることこそが肝要である」と、学問の本質を強調しています。
こうして見ていくと、本居宣長の学問の理念は、現代においても「継続力」や「自分の軸を持つこと」の重要性を教えてくれるものだと言えるでしょう。
本居宣長記念館(三重県松阪市)
本居宣長は1730年に松阪に生まれ
松阪で町医者を営みながら
日本の古典文学の研究を行った。
それまで誰も読めなかった古事記を
35年を費やして解読し
「古事記伝」を執筆。
師匠である賀茂真淵とともに
国学の四大人のうちの1人。
写真は撮影OKの自画自賛像🎨✨️ pic.twitter.com/URS36WLN2i— Metaro🎵 (@metaro_mech) March 21, 2025
本居宣長 もののあはれとは何か
「もののあはれ」とは、本居宣長が日本文学の本質として重視した感情や美意識を表す言葉です。
簡単に言えば、目に見える出来事や人の心の動きに対して、しみじみとした感動や共感を覚えることを指します。
宣長は特に『源氏物語』を通じて、この「もののあはれ」の考え方を深めました。
彼は、物語の登場人物の喜びや悲しみを丁寧に読み取り、その感情の繊細な描写に日本文化の核心があると考えたのです。
人間の感情に寄り添い、理屈ではなく心で感じ取る姿勢が、日本独自の文学精神だと主張しました。
一方で、「もののあはれ」は単に感傷的であればよいというわけではありません。
宣長は、過剰な理屈や道徳ではなく、人として自然に湧き上がる感情を大切にすることが、真の教養につながると見ていました。
これは、当時主流だった儒教的な「正しさ」重視の思想に対する、明確な対抗でもあります。
ただし、現代の感覚では「感情的すぎる」「主観的すぎる」と感じられる側面もあります。
論理性を重視する現代社会とは異なる価値観であるため、受け止め方には注意が必要です。
それでも、「もののあはれ」という感性は、四季の移ろいや人の営みに美しさを見いだす日本文化の土台のひとつです。
本居宣長は、それを言葉として定義し、後世に残したことで、日本人の精神的な在り方に大きな影響を与えました。
門弟たちは身分や地域を問わず多岐にわたり、武士、神官、医師、商人などさまざまな立場の人が宣長のもとを訪れました。
学びの場は宣長の自宅「鈴屋」であり、彼は診療を終えた後、夜な夜な講義を行いました。
そこでは『古事記』や『源氏物語』の注釈だけでなく、日本語や文化の本質についても熱心に語られたと伝えられています。
全国に広がった門弟と国学の発展
本居宣長の学問は、彼一人の努力にとどまらず、全国に広がった多くの門弟たちによってさらに発展していきました。
その数は生前だけで500人近くにのぼったとされており、松阪の一地方から全国へと国学の流れが波及した背景には、宣長の教えに感銘を受けた人々の存在があります。
門弟たちは身分や地域を問わず多岐にわたり、武士、神官、医師、商人などさまざまな立場の人が宣長のもとを訪れました。
学びの場は宣長の自宅「鈴屋」であり、彼は診療を終えた後、夜な夜な講義を行いました。
そこでは『古事記』や『源氏物語』の注釈だけでなく、日本語や文化の本質についても熱心に語られたと伝えられています。
このような学びの輪は、やがて各地に広がり、弟子たちが自ら講義や研究を行うことで国学が日本全体へと根づいていきました。
その中には、後に尊王攘夷運動に影響を与える思想を持った人物も含まれており、学問が政治的思想の源泉となる一面も持ち合わせていたのです。
一方で、国学はあくまで古典に基づく日本固有の精神や価値観を重んじる学問であるため、時代の変化とともに受け止め方に差が出ることもありました。
宣長の教えをどう解釈するかは、弟子それぞれに委ねられていたため、後年になるほど幅の広い思想的展開を見せるようになります。
このように、本居宣長の学問は一代限りのものではなく、教えを受け継いだ門弟たちが全国で活動を展開したことで、国学という学問体系が確立されていきました。
それは、日本人が自らの文化や言葉、精神を見つめ直すきっかけにもなり、今なお研究対象として重要な意味を持ち続けています。
本居宣長 何がすごい?人物像と逸話から見る魅力
本居宣長 エピソードと人柄
本居宣長は、厳格な学者という印象とは裏腹に、繊細で情に厚い人物でした。
彼の人柄をよく表しているのが、「鈴」と「山桜」への深い愛情です。特に書斎には大小さまざまな鈴を飾り、気分転換に鳴らしていたといいます。
そのことから、地元では「鈴の先生」と親しまれ、自らの書斎を「鈴屋」と名付けるほどでした。
また、彼は非常に几帳面な性格で、医師としての診察記録や処方内容を毎日欠かさず記録していました。
診察が正月に重なっても断らず、遠方の往診にも対応していたという逸話も残っています。
これは単に真面目というだけでなく、人々への思いやりがあったからこそ続けられた姿勢だと考えられます。
一方で、学問に対しては非常に厳しく、自身の弟子たちにも徹底した学びの姿勢を求めました。
ただし、頭ごなしに叱るのではなく、丁寧に導く姿勢が評価され、多くの弟子が自然と彼の元に集まりました。
最終的には、全国におよそ500人近い門弟を持つほどになりました。
さらに、生前に自分の墓の設計を行い、好きだった山桜を墓所に植えるように遺言したことも、本居宣長らしいエピソードのひとつです。
実際に、その墓は今でも松阪市の妙楽寺に残され、春になると満開の桜が彼を包むように咲き誇ります。
このように、本居宣長は学者である前に、一人の人間として豊かな感性と誠実な心を持ち続けていたことが、多くの人々に支持された理由の一つと言えるでしょう。
鈴と山桜を愛した「鈴屋」の学者
本居宣長の人柄を語るうえで欠かせないのが、「鈴」と「山桜」への深い愛情です。
彼は書斎に数十個の鈴を飾り、気分転換や心を落ち着けるために静かに鈴を鳴らしていたと伝えられています。
この行動には、日々の学問に向き合う中で、自分の心を整えるための小さな習慣があったことがうかがえます。
この書斎は「鈴屋(すずのや)」と名付けられ、まさに本居宣長の世界観を象徴する場所でした。
研究に集中する場でありながら、彼の感性や美意識が反映された空間だったのです。
また、町の人々もその存在をよく知っており、「鈴が鳴っている間は先生が勉強している」と認識していたそうです。
もう一つ、彼が特に好んだのが「山桜」でした。
この花は、華やかさよりも自然な美しさや素朴さが際立つ品種であり、宣長の価値観と重なるものがあります。
彼は和歌にも山桜をたびたび詠み、日本人の心を象徴する存在として重ね合わせていました。
象徴的なのは、彼の墓所に山桜が植えられていることです。
これは本人の遺言によるもので、死後もなお自然とのつながりを大切にしたいという強い思いが込められています。
現在でも春になるとその桜は咲き誇り、多くの人が訪れる場所となっています。
このように、「鈴」と「山桜」は本居宣長にとって単なる好きな物ではなく、学問と生き方そのものを支える精神的な柱だったといえるでしょう。
それが、彼を「鈴屋の学者」と呼ぶにふさわしい理由です。
「しき嶋のやまとごゝろを人とはゞ朝日にゝほふ山ざくら花」
(本居宣長)
大和心、大和魂とは、何か?「日本人である私の心とは、朝日に照り輝く山桜の美しさを知る、その麗しさに感動する、そのような心です。」と本居宣長は、答えたと言います。 pic.twitter.com/iivWNIL9Mc
— 原口 一博 (@kharaguchi) August 3, 2020
医業のかたわら続けた学問生活
本居宣長は医師として生計を立てながら、一方で学問の道を決してあきらめませんでした。
昼間は患者の診察を行い、夜になると書斎にこもって古典の研究や講義に没頭する生活を長年続けたのです。
松坂で内科・小児科を開業したのは28歳のときでした。
診察は非常に真面目で、正月でも休まず往診を行ったという記録が残っています。
遠方の患者にも親身に対応し、必要があれば母親の体調まで診るなど、患者全体を見ようとする姿勢が特徴的でした。
しかし、本人にとって医業はあくまで「生活のための手段」に過ぎなかったようです。
むしろ本当に情熱を注いでいたのは、古典文学や国学の研究でした。
診療を終えたあとの時間をすべて学問に充て、少しずつ『古事記伝』や『源氏物語』の注釈書をまとめていきました。
このような生活は決して楽ではなく、時間のやりくりや体力的な負担もあったはずです。
それでも宣長は学びを止めず、結果として多くの著作を後世に残しました。
また、松坂の自宅では講義も行っており、近隣や遠方からも弟子が集まってきました。
まさに「医師でありながら教師でもあった」と言える存在です。
このように、医療と学問の両立という二重生活を40年以上続けた姿勢は、多忙な現代人にとっても示唆に富んでいます。
限られた時間の中でも、意志と工夫次第で本当に大切なことに打ち込める――それを本居宣長は、自らの生き方で証明してくれた人物でした。
本居宣長 死因と最期の言葉
本居宣長は、1801年(享和元年)9月29日に71歳でこの世を去りました。
死因は明確には記録されていませんが、高齢による衰弱と見られています。
亡くなる直前まで医師として患者を診察していたことからも、心身ともに限界まで働いていた様子がうかがえます。
晩年の彼は、学問活動を続けながらも体調の変化を自覚していたようで、生前から自らの死後について非常に細かく準備をしていました。
特に注目されるのは、彼自身が書き残した「遺言書」の存在です。
この中には、葬儀の方法、墓の設計、供養の仕方に至るまで詳細な指示が書かれており、死後の姿まで自分の理想で整えたいという強い意志が見て取れます。
また、最期の言葉について明確な記録は残されていないものの、彼が晩年に書き遺した文や書簡の中には、命あるうちに『古事記伝』を完成させることができた喜びや、弟子たちへの感謝の気持ちが多く表れています。
そこからは、「学問を通じて生きる意味を見出した人」としての満足感が読み取れるでしょう。
なお、宣長の墓は三重県松阪市の山室山にあり、本人の遺言に従って設計されたものです。
墓の背後には、彼が生前愛した山桜が植えられており、今も毎年春になると満開の花が彼の眠る場所を彩ります。
このように、本居宣長の最期は、学問に生き、準備を整え、静かに人生を終えた姿として語り継がれています。
最期の瞬間までも「学者らしさ」を貫いた人物だったと言えるでしょう。
生前に設計した墓と遺言の詳細
本居宣長は、自身の死後についても極めて細やかな準備をしていたことで知られています。
とくに注目すべきは、彼が生前に自らの墓を設計し、遺言書にその仕様を詳細に記していた点です。
これは、当時としても非常に珍しいことであり、彼の几帳面な性格と、死後も自らの思想や美意識を大切にしたいという思いが強く表れた行動でした。
墓は三重県松阪市の山室山にある妙楽寺の奥に設けられています。
この場所は、彼自身が生前から好んでいた静かな丘の上で、遠く松阪の町を一望できる地です。
墓石はシンプルながらも力強い形をしており、背後には本人の希望により「山桜」の木が植えられました。
毎年春になると、この桜が咲き誇り、訪れる人々の目を楽しませています。
遺言書には、供養の方法や法事の日取り、墓所の管理に関する指示までが記されており、その内容は数十項目に及ぶほど細かいものでした。
年忌法要のあり方、墓前で読経する経典の種類、使用する道具に至るまで配慮が行き届いていました。
これらの指示は、すべて弟子たちや家族が実行に移し、今なおその精神は受け継がれています。
このように、宣長の死後に関する準備は、単なる形式的なものではなく、学問に対する姿勢や自然への愛情、自身の生き方を後世に伝えるための“最後のメッセージ”でもあったと言えるでしょう。
その意志の強さと美意識は、今も墓を訪れる多くの人に深い印象を与えています。
本居宣長の思想が与えた時代への影響
本居宣長の思想は、学問の枠を超えて、江戸時代後期から明治維新へと向かう日本社会全体に大きな影響を与えました。
とくに、彼が提唱した「大和心(やまとごころ)」や「もののあはれ」といった日本固有の精神性を重視する考え方は、国学という学問の核となり、多くの学者や思想家に継承されていきます。
当時の知識人の多くは、儒教や仏教など中国由来の思想を重んじていましたが、宣長はそれらを「漢意(からごころ)」と呼び、日本本来の価値観を見失わせるものとして批判しました。
そのうえで、古代の文献や言葉から日本人の精神の源を探る「古道(こどう)」の探求を重視しました。
こうした姿勢が、思想面での独立性や自国文化への自覚を促したのです。
この思想は、やがて幕末の「尊王攘夷運動」にもつながっていきます。
宣長の弟子や影響を受けた学者たちは、「天皇を敬い、外来のものを排するべきだ」という考え方を展開し、それが政治運動として拡大していきました。
尊王思想は、結果的に幕府の体制を揺るがす力となり、明治維新の思想的な下地のひとつにもなったのです。
ただし、宣長自身は政治的な改革や過激な行動を望んでいたわけではありません。
あくまで学問の立場から、古代の精神に学ぶことを説いていたにすぎません。
それにもかかわらず、後世の人々がその思想をどう受け取り、どのように広げていったかによって、大きな歴史的転換が生まれました。
このように、本居宣長の思想は学問の枠を越え、時代の流れを動かす原動力となった一面を持っています。
古典を通して精神性を掘り下げたその視点は、文化・思想・政治にまで影響を及ぼすほどの力を持っていたのです。
本居宣長 何がすごいのかを一目で理解できる総まとめ
- 『古事記』を35年かけて注釈し『古事記伝』全44巻を完成させた
- 読解困難だった古典文献を精密に解析し、後世の研究に道を開いた
- 外来思想に頼らず、日本独自の精神文化を重視した
- 「やまとごころ」や「もののあはれ」など日本固有の価値観を提唱した
- 『源氏物語玉の小櫛』など文学の本質を感性で読み解く姿勢を示した
- 医業と学問を両立し、昼は診察・夜は研究を続けた
- 全国から約500人の門弟を集め、学問を広く伝えた
- 学問の姿勢として「継続」と「誠実さ」を重視した
- 教養とは理屈ではなく感情への共感にあると説いた
- 死後の供養や墓の設計まで自らの美意識で整えた
- 日本語の文法や音韻にも深い研究を行い、日本語学の礎を築いた
- 儒教・仏教の形式主義に対して感性重視の思想を打ち出した
- 明治維新期の尊王攘夷思想に間接的な影響を与えた
- 書斎「鈴屋」や山桜など、自然や風雅を愛する一面があった
- 学問の成果が政治や文化を動かす力になることを示した
なにスゴ博士の感想コーナー・研究メモ
本居宣長って、ちょっと堅そうな名前に聞こえるかもしれませんが、その生き方や考え方を知ると、とても人間味あふれる人物だったことがわかります。
古い時代のことを、何十年もかけてコツコツと調べて、今の私たちが日本の文化や心を見つめ直すきっかけをくれた人。それが本居宣長です。
学問に真剣に向き合いながらも、鈴を愛し、桜を大切にした柔らかな感性も持ち合わせていた彼の姿は、今の時代にも通じるものがたくさんあります。
「本居宣長 何がすごい?」と思ってこのページを訪れたあなたにとって、少しでもその魅力やすごさが伝わっていたら嬉しいです。
気になった方は、ぜひもう少し深く調べてみてくださいね。