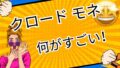あなたは「江夏の21球 何がすごい?」と検索して、この記事にたどり着いたのではないでしょうか。
確かに、野球に詳しくない人にとっては、ただの9回裏のピンチを切り抜けたシーンに見えるかもしれません。
しかし、あの21球には、スポーツを超えた“人間のドラマ”が凝縮されていたのです!
1979年の日本シリーズ第7戦。
勝てば球団初の日本一という状況で、1点差のまま迎えた最終回!!
マウンドには、当時広島東洋カープのリリーフエースだった江夏豊。
彼が投じた21球には、「江夏の21球 自作自演」という疑念が出るほどの展開があり、「江夏の21球 キャッチャー」水沼との信頼関係や、「江夏 スクイズ外し」に象徴される神懸かり的な判断力も詰まっていました。
実際、あの試合を見た多くのファンが、ただの野球の一場面ではない“何か”を感じ取っています。
そして今でも、「江夏の21球 本」や「江夏の21球 動画」を探し、その凄さを改めて確かめようとする人が絶えません。
では、なぜこのたった21球が、40年以上経った今でも語り継がれるのでしょうか?
その“すごさ”の本質とは何なのか!?
この記事では、江夏の21球に隠された心理戦、駆け引き、そしてチーム内外のドラマまで、さまざまな視点からその魅力を紐解いていきます。
読むことで、あなたの中にも「なぜこれが語り継がれるのか」が、きっと腑に落ちるはずです。
1979年の近鉄対広島の日本シリーズ第7戦で、1点リードの9回裏に無死満塁のピンチに陥るも近鉄打線を抑え、広島を初の日本一に導いたストッパー・江夏豊がこの試合で投げた球数は21球…と思われがちだが、実は41球。
21球は9回裏に投じた球数で、この試合に江夏は7回途中から登板している。 pic.twitter.com/z6mo4amr30— キタトシオ (@kitatoshio1982) September 27, 2024
江夏の21球 何がすごいのかを解説
江夏の21球とはどんな試合だったか
「江夏の21球」とは、1979年のプロ野球・日本シリーズ第7戦において、広島東洋カープの抑え投手・江夏豊が、試合終盤の9回裏に投じた21球のことを指します。
この試合は、セ・リーグの広島とパ・リーグの近鉄バファローズが3勝3敗で迎えた最終戦で、どちらが勝っても球団史上初の日本一という、極めて重要な一戦でした。
舞台は大阪球場。広島が1点リードのまま迎えた9回裏、江夏がマウンドに上がります。ここから始まる21球は、ただの投球記録ではありません。
1球ごとにドラマがあり、選手の心理、戦略、ミスや好プレーが複雑に絡み合っていきます。
無死一塁から始まった近鉄の攻撃は、盗塁や四球、敬遠などを経て、やがて無死満塁の大ピンチに変わっていきました。
サヨナラ負けの可能性もある中で、江夏は一人ひとりの打者に全力で立ち向かい、最終的に三振で試合を締めくくります。
この21球が特別な理由のひとつは、江夏が抱えた「孤独な戦い」にあります。
ブルペンでは交代準備が進み、チームからの信頼に疑念を持ちながらも、自らの誇りと責任で勝負を続けました。
そして、キャッチャーの水沼四郎との連携もこの21球を支えた大きな要素です。
捕手がサインを出し、投手が首を振らずに全てに応える。
この信頼関係が、極限の場面での力を引き出しました。
こうした背景が重なり、「江夏の21球」は今なお語り継がれる名シーンとして、多くの野球ファンや関係者の記憶に残り続けています。
江夏の21球 自作自演という見方とは
「江夏の21球」は、野球史に残る名場面として知られていますが、一部では「自作自演だったのではないか」という見方も存在しています。
この考え方の背景には、江夏豊自身がピンチを招き、そのピンチを自らの力で乗り越えたという構図があります。
つまり、「自分でランナーを出し、自分で抑える」という展開が、まるでドラマのようにできすぎていると感じる人もいるということです。
たとえば、無死からの出塁、盗塁、四球、敬遠などで満塁のピンチを迎えますが、最終的には三振で試合を締めくくっています。
この一連の流れが「演出のようだ」と見られることがあります。
ただし、野球は偶然の積み重ねで成り立つスポーツです。
投手が意図してピンチを作ることは極めて稀で、実際にはミスや采配、相手の作戦など複数の要素が絡み合って試合が展開されます。
また、江夏の投球は完璧ではなく、送球ミスや盗塁成功などによって状況が悪化したのも事実です。
これらはコントロール不能な要素であり、あえてピンチを作ったとは言い難い側面があります。
このように、「自作自演」という表現は少々誇張された見方であるとも言えますが、それほどまでにこの21球の流れがドラマチックだったという証でもあります。
いずれにしても、観客の心を動かす試合展開だったことは間違いありません。
そこに“演出”のような印象を抱く人がいても、不思議ではないのかもしれません。
江夏の21球 キャッチャー水沼の存在
「江夏の21球」が名シーンとして語り継がれる背景には、キャッチャー・水沼四郎の存在が大きく関わっています。
この試合での江夏と水沼のバッテリーは、極限状態の中でも互いに信頼し合い、息の合ったプレーを続けました。
とくに注目されるのは、江夏が最後まで一度も水沼のサインに首を振らなかったことです。これは、二人の間に強い信頼関係があったことを象徴しています。
水沼は試合中、スクイズの可能性を察知して咄嗟に立ち上がり、投球をミットでしっかりと捕球しました。この判断と動きがなければ、ボールは暴投となり、試合は同点、もしくは逆転サヨナラという結果になっていたかもしれません。
また、試合前から江夏の球種やクセ、そして相手打者の傾向を把握していた水沼は、プレッシャーのかかる場面でも落ち着いてリードを続けました。
とくに、ピッチャー心理が不安定になりがちな満塁の場面で、ストライクとボールを巧みに使い分ける配球は見事でした。
こうした冷静なリードと判断力は、表には見えにくいものの、江夏の投球内容に大きな影響を与えていました。
捕手としての技術だけでなく、心理的な支えとしての役割も果たしていたと言えるでしょう。
言ってしまえば、「江夏の21球」は、投手一人の力ではなく、水沼の存在があったからこそ完成した名シーンだったのです。
江夏 スクイズ外しが見せた判断力
「江夏の21球」の中でも、とりわけ多くの人に語り継がれているのが“スクイズ外し”の場面です。
このプレーは、9回裏・一打逆転サヨナラという極限の状況で起こりました。
近鉄の打者・石渡茂がバントの構えを見せ、三塁ランナーがスタートを切った瞬間、江夏は即座にそれを察知し、カーブの握りのまま投球を外角高めに大きく外しました。
このスクイズ外しが「判断力の極み」と言われるのは、いくつかの理由があります。
まず、江夏は左投手であるため、三塁ランナーの動きが視界に入りにくいという不利があります。
それにもかかわらず、打者の構えや捕手・水沼の動き、そしてこれまでの試合展開から瞬時にスクイズを読み取ったのです。
さらに注目すべき点は、その投球が「カーブの握りのまま」だったことです。
通常、ウエスト(ボールを大きく外すこと)はストレートで行われます。カーブで外すには制御が非常に難しく、暴投のリスクも高くなります。
しかし、江夏はそのリスクを承知の上で、わずか数秒の判断でこの選択を実行しました。この大胆で正確な対応が、スクイズの失敗を引き起こし、試合の流れを大きく変えるきっかけとなったのです。
このときの判断には、経験だけでなく直感や洞察力も関わっていたと考えられます。
江夏自身も「もう一度同じ状況で同じことができるかと聞かれたら、自信はない」と語っており、まさに“神業”に近いプレーだったことがわかります。
この一球がなければ「江夏の21球」はこれほどまで語り継がれるものにはならなかったかもしれません。
言い換えれば、このスクイズ外しこそが、江夏という投手の凄さを象徴する象徴的な一球なのです。
江夏の21球 本からわかる真実とは
「江夏の21球」という言葉を最初に世に広めたのは、スポーツノンフィクション作家・山際淳司による同名の作品です。
この短編は、1980年に創刊された雑誌『Sports Graphic Number』の創刊号に掲載され、後にエッセイ集『スローカーブを、もう一球』にも収録されました。
試合の表面的な記録だけでなく、選手たちの心理や葛藤、グラウンドの外で交わされた言葉まで丁寧に描写されています。
特に印象的なのは、9回裏の21球を「ただのプレーの連続」とは見なさず、選手たちの内面にまで踏み込んで表現している点です。
江夏が味方ベンチの采配に不信感を抱き、それが精神的な揺らぎを生んでいたこと。
あるいは、一塁手・衣笠祥雄がタイミングを見て江夏にかけたひと言が、彼の集中力を呼び戻したこと。
こうした細やかな描写は、本を通じてしか知り得ない情報です。
また、試合をテレビで観ていた人や新聞記事で結果を知った人では把握しきれなかった、プレーとプレーの“間”にある緊張感も、文章を通じてじっくり伝わってきます。
これにより、多くの読者が「これは単なる試合ではなく、一つのドラマだ」と感じるようになりました。
ただし、この作品にはあくまで著者の視点や表現が含まれているため、事実と演出の境界線に立つ読み方が求められます。
実際、当時の関係者が後年に語った証言と異なる点もいくつか存在しています。
とはいえ、野球というスポーツの魅力を人間ドラマとして描き出し、その後のスポーツノンフィクションの流れを作ったという意味では、この本は非常に大きな意義を持っています。
今でも多くの人に読み継がれている理由は、記録以上の“真実”がそこにあると感じられるからでしょう。
江夏の21球 何がすごいのか映像で知る
江夏の21球 動画から見る緊張の21球
「江夏の21球」は文章だけでも十分に迫力を感じられる名場面ですが、当時の映像を視聴することで、その緊張感や空気感はさらにリアルに伝わってきます。
1979年の日本シリーズ第7戦は、現在もNHKやBSなどで断続的に再放送されており、YouTubeなどで一部のシーンを視聴できることもあります。
実際の映像を見ると、球場全体が静まり返った瞬間や、スタンドのざわめき、選手たちの表情からも“ただごとではない空気”が感じられます。
特に注目すべきは、19球目のスクイズ外しの場面です。このシーンでは、江夏が投球モーションに入った瞬間に三塁ランナーがスタートを切り、打者がバントの構えを見せます。
観ている側も思わず息をのむような一瞬で、ボールが高めに外れ、キャッチャー水沼がしっかりとミットに収める場面は、まさに映像でこそ味わえる迫力があります。
また、映像を通じて分かるのは、江夏の動作の速さや無駄のなさ、そして投球後の表情の変化です。
カメラが捉える横顔や仕草からは、静かな闘志と冷静さが見て取れます。文字では表現しきれない“間”の演技のような緊張感が、動画には詰まっているのです。
ただし、当時の中継映像はすべて残っているわけではなく、後年に編集・再構成されたドキュメンタリー映像も多く流通しています。
中にはナレーションや演出が加わっているものもあるため、視聴する際はその点に注意が必要です。
とはいえ、動画で見る「江夏の21球」は、単なる記録の映像ではなく、“野球というスポーツが生む極限のドラマ”を肌で感じられる貴重な資料です。プレーの一つひとつが、見る者の心に迫ってくる力を持っています。
江夏の21球に学ぶ心理戦と駆け引き
「江夏の21球」は、単なるピッチングの連続ではなく、選手同士の高度な心理戦と駆け引きが随所に見られる試合でもあります。
この試合では、投手・江夏豊が物理的な球威だけでなく、相手打者や自軍ベンチとの“目に見えないやり取り”を制した点に注目すべきです。
9回裏の初球からヒットを許してランナーを背負った場面では、ただ守るのではなく、相手が何を考えているか、次に何を仕掛けてくるかを読みながら、配球と守備体形を変えていきました。
印象的なのは、無死満塁での“スクイズ警戒”のシーンです。
ここでは単に打者に対して集中するだけでなく、ランナーの動きやベンチのサイン、打者の表情から「ここで何か動く」と直感し、すぐに反応した江夏の読みが勝負を分けました。
また、近鉄ベンチも代打や盗塁などを駆使し、プレッシャーをかけ続けていました。
それに対して江夏は、相手の狙いを見抜いたり、あえてボール球を投げて手を出させるなど、心理的に一歩上を行く投球を重ねています。
さらに、江夏とバッテリーを組むキャッチャー・水沼のリードも重要です。
的確なサイン、間の取り方、敬遠のタイミングまで含め、打者の心理を揺さぶる手法がいくつも使われています。
こうして見ると、「江夏の21球」はただの名勝負ではなく、相手の裏をかく冷静さと、駆け引きの技術が結集した“心理戦の教科書”とも言える内容です。
野球に詳しくない人でも、人と人との読み合いという視点で見ると、さらに奥深さを感じられる場面がいくつも見つかるでしょう。
江夏の21球とキャリアハイライトの関係
「江夏の21球」は、江夏豊という投手のキャリアにおいて、最も象徴的な場面の一つとして知られています。
プロ入りから通算206勝を挙げ、記録にも記憶にも残る投手だった江夏ですが、キャリア終盤にリリーフに転向し、新たな役割で結果を残したことが、彼の選手人生に深みを与えました。
その中でも、この「21球」は、抑え投手としての真価が問われる極限の場面で見せた圧巻のパフォーマンスです。
特筆すべきは、それまで先発完投型として活躍してきた江夏が、広島移籍後に抑えへとコンバートされていた点です。
リリーフとしての江夏は、1点差での登板や、満塁のピンチといった重圧を常に背負う役割を担っていました。その最たる象徴が、日本シリーズ第7戦での「江夏の21球」です。
ここでは、単に試合を締めたという事実だけでなく、打者との駆け引き、味方ベンチへの複雑な思い、味方選手からの支えなど、江夏の投手人生を凝縮したようなドラマが展開されました。
このシーンが後世まで語り継がれるのは、彼の持つ野球観や勝負へのこだわりが、その21球すべてに詰まっているからです。
ピンチで見せる冷静さ、相手の裏をかく判断力、そして自らのプライドを守り抜く気迫。それらすべてが、江夏という投手の“完成形”とも言える瞬間でした。
こうして「江夏の21球」は、数々の記録に彩られた彼のキャリアの中でも、特に人々の記憶に残るハイライトとして、今も語り継がれているのです。
江夏の21球が評価される3つの理由
「江夏の21球」が長年にわたって語り継がれ、今でも多くの人に評価され続けているのには、明確な理由があります。ここでは特に重要とされる3つのポイントを紹介します。
1つ目は、極限状態での冷静な判断力です。
日本シリーズ第7戦、9回裏の1点リードという状況は、どんな選手にとっても大きなプレッシャーになります。
そこに無死満塁という最大級のピンチが重なったにもかかわらず、江夏は一球一球に集中し、的確な配球と制球を続けました。スクイズを見抜いて外した場面に代表されるように、瞬間的な判断力の鋭さが光りました。
2つ目は、試合を支えた人間ドラマの存在です。
この21球には、江夏自身の自尊心と葛藤、ベンチとのすれ違い、一塁手・衣笠との信頼関係など、チーム内外の感情が複雑に絡み合っています。
単なるスポーツの一場面ではなく、「人が本気で何かと向き合うときにどんな心の動きがあるか」というテーマを浮かび上がらせている点が、多くの読者や視聴者の心を打つ要因です。
3つ目は、野球という競技の奥深さを伝えた点です。
このシーンでは、ストレートとカーブの配球の意図、守備陣形の選択、敬遠策など、野球というスポーツがいかに繊細な駆け引きで構成されているかが如実に現れています。
特に江夏とキャッチャー水沼とのサインプレーは、単なる技術以上の“意志の共有”とも言えるものでした。
これらの要素がひとつに重なったことで、「江夏の21球」は単なる名場面ではなく、時代を超えて語られる“スポーツの金字塔”となったのです。
江夏の21球と現代野球の違い
「江夏の21球」が行われた1979年当時の野球と、現在のプロ野球とでは、戦術面や選手起用の考え方に大きな違いがあります。
特に、投手の使い方や試合運びのスタイルに注目すると、そのギャップはより明確に見えてきます。
まず、当時は今ほど「分業制」が確立されていませんでした。
先発投手が最後まで投げきることも珍しくなく、リリーフの役割も現在ほど専門的ではありません。
江夏は本来、先発完投型としてキャリアを積んできましたが、広島では抑えに転向し、まさに1点を守りきるという重要な場面で登板するようになっていました。
現代の野球では、セットアッパーやクローザーがそれぞれ決まっており、データに基づいて綿密に起用されます。
試合終盤の投手交代はリスク管理として当たり前の戦略です。一方で、江夏のように最後の3イニングを一人で投げるようなケースは、現代ではほとんど見られません。
また、現在は球速や回転数などの投球データが重視される傾向があります。
しかし「江夏の21球」では、感覚や経験、読みの鋭さが勝負の鍵を握っていました。
たとえばスクイズを直感で見抜いた19球目のように、データに頼らずとも選手自身の判断で動く場面が多く見られたのです。
さらに、監督の采配スタイルにも違いがあります。現代のベンチワークは、AIやアナリストが裏で支えることも増えており、数字とロジックに基づく判断が求められます。
一方で古葉監督は、選手の感情や空気を読みながら場を動かしていたのが印象的です。
このように、江夏の21球には今では見られない“人間味のある野球”が凝縮されています。合理性が重視される現代において、この一戦が「ドラマ」として語り継がれるのは、数字では測れない価値がそこにあったからです。
江夏の21球の評価が分かれる理由
「江夏の21球」は、多くの野球ファンやメディアから高く評価されている一方で、一部からは疑問や批判の声も上がっており、その評価が分かれる場面も見られます。
まず、肯定的に評価される理由としては、極限のプレッシャーの中で21球を投げきり、広島を球団史上初の日本一に導いたという結果が大きいでしょう。
心理戦、技術、チームプレーなど、野球のすべてが詰まった場面として称賛されています。特にスクイズを外した判断や、サインに一度も首を振らなかった信頼関係は、今でも「美談」として語り継がれています。
しかし一方で、「評価が過剰ではないか」という声も存在します。その理由のひとつが、江夏自身がピンチを招いた張本人であるという点です。
ヒットを打たれ、盗塁を許し、エラーや四球で無死満塁を作ってしまったことで、「自分で苦境を招き、自分で解決しただけ」と見る向きもあります。
また、後年のインタビューやドキュメンタリーによって、「実はあの時のスクイズ外しは偶然だったのでは?」といった別の視点が語られることも、評価の割れる要因になっています。
完全な神業と見るか、運の要素も絡んだ結果と見るかは、受け取る側の考え方によって異なります。
加えて、演出やドラマ性を強調したメディアの報道に対して、「感動ありきの物語に仕立てすぎている」と感じる人も少なくありません。
試合全体の流れを無視して21球のみにスポットを当てる構成は、他の選手の活躍や背景を置き去りにしているという指摘もあります。
このように、「江夏の21球」が評価されるのは間違いありませんが、その捉え方は一面的ではなく、多角的な視点で見ていく必要があります。
名シーンであるからこそ、肯定も否定も生まれ、それが今なお語られ続ける理由のひとつとも言えるでしょう。
江夏の21球 何がすごいのかを総括してわかりやすく解説
-
日本シリーズ第7戦という最も重圧のかかる場面での登板
-
無死満塁のピンチを一人で切り抜けた精神力と集中力
-
スクイズを直感的に見抜き、カーブの握りのまま外すという高度な対応
-
一度もキャッチャーのサインに首を振らなかったバッテリーの信頼関係
-
チームからの信頼に揺らぎながらも最後までマウンドに立ち続けた覚悟
-
水沼捕手の冷静なリードと即時の判断が投手の力を最大限に引き出した
-
投球だけでなく、心理戦と駆け引きの応酬が展開された試合展開
-
ファンや関係者の記憶に長く残るほどの劇的な試合構成
-
ドラマ性が強く、試合の流れ自体が一種の物語として評価されている
-
自作自演と捉えられるほどの「できすぎた展開」が議論を呼んだ
-
ノンフィクション作家によって詳細に描かれ、文化的にも注目された
-
現代野球とは異なり、選手自身の判断と感覚が問われるシーンが多かった
-
江夏のキャリアを象徴する場面として、後世にまで影響を与えた
-
映像からも緊迫感と空気感が伝わり、視覚的なインパクトが大きい
-
名場面としてだけでなく、野球の奥深さと人間性が凝縮されている
なにスゴ博士の感想コーナー・研究メモ

いや〜、これは本当にすごかった!
「江夏の21球」って聞いたときは、ただピンチを切り抜けた投球だと思ってたけど、調べれば調べるほど、その裏にある心理戦やチームの空気感、そして“人間ドラマ”にグッとくるね。

とくに印象的だったのは、キャッチャー水沼さんとの無言の信頼関係と、スクイズ外しの一球。
あれはもう、野球っていうより映画のワンシーンのような緊張感だったよ!!

それに、「江夏の21球 自作自演」って見方もあって、ちょっと意外だったけど、それだけこの試合がドラマチックだったってことなんだなと納得!!

本や映像で振り返るのもおすすめ!
知れば知るほど、ただの野球じゃないって思えるし、「何がすごいのか」がはっきり見えてくる!!

これからも、こんな“語り継がれる名シーン”を見つけて、どんどん研究していきたいと思います!
それではまた、次回の“なにスゴ研究”でお会いしましょう〜!